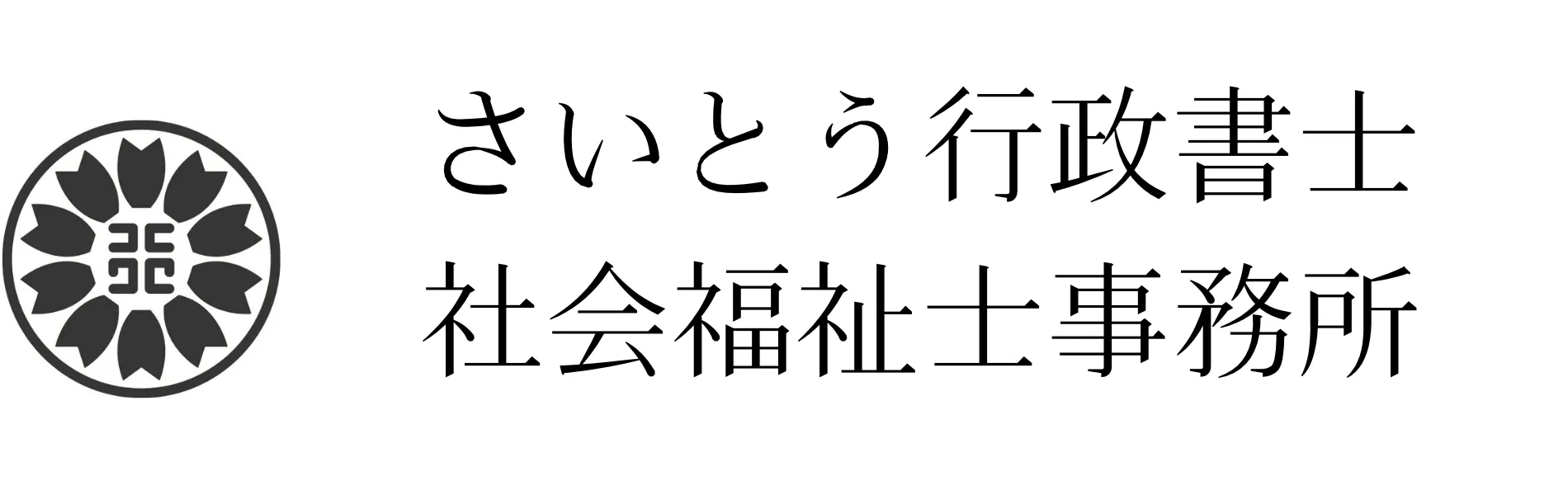相続に関する資格について
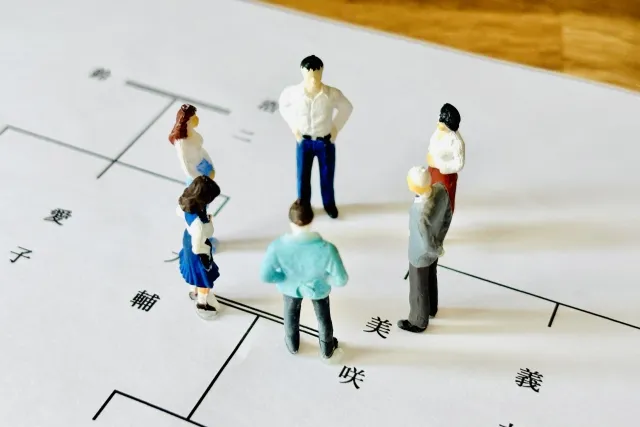
相続に関する問題が発生した時に誰に相談したほうが良いか、悩んでしまうことがあるかと思います。相続に携わることができる専門家のできること、できないこと、業務内容等をまとめました。また、相続に関する民間資格についてもまとめています。
| 士業 | できること | できないこと |
|---|---|---|
| 弁護士 | ・相続に関するすべての法律相談・遺産分割協議の代理・遺留分侵害額請求の代理・調停・訴訟での代理人活動・遺言執行者としての手続き | 特になし(相続分野での代理権は全面的に認められる) |
| 司法書士 | ・相続登記(不動産名義変更)・遺産承継業務(相続財産の分配サポート)・家庭裁判所提出書類の作成支援(相続放棄など) | ・代理交渉(遺産分割協議の当事者代理は不可)・訴訟代理(簡裁代理権はあるが相続事件は対象外が多い) |
| 行政書士 | ・遺言書作成のサポート(公正証書遺言の原案作成)・相続人調査(戸籍収集)・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成 | ・登記(司法書士の業務)・相続税申告(税理士の業務)・裁判や調停の代理(弁護士の業務) |
| 税理士 | ・相続税・贈与税の申告・財産評価(不動産・株式などの税務上評価)・節税対策の提案・税務調査への対応 | ・登記業務(司法書士の業務)・裁判・調停の代理(弁護士の業務)・遺産分割協議書そのものの作成(行政書士や弁護士) |
弁護士の相続業務
弁護士は、相続に関するあらゆる法律問題を取り扱える唯一の専門家です。まず、生前の段階では、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成支援を行い、内容が法的に有効かどうか、また相続人の遺留分を侵害していないかを確認します。必要に応じて遺言執行者に就任し、将来の相続に備えることも可能です。また、家族信託や事業承継の仕組み作りなど、複雑な資産承継スキームの設計にも対応できます。
相続が開始した後は、相続人の調査や相続関係説明図の作成を行い、遺産分割協議において代理人として交渉にあたります。特に、遺産の分け方で意見が対立する場合や、遺留分侵害額請求が問題となる場合には、弁護士が相続人を代理して交渉や調停、さらには訴訟まで対応できます。また、相続放棄や限定承認といった家庭裁判所への手続きも代理でき、債務超過の相続にも対応可能です。
さらに、家庭裁判所での遺産分割調停や遺留分調停、地方裁判所での相続訴訟など、裁判手続きに関しても弁護士が代理人として活動できます。これは司法書士や行政書士にはできない、弁護士だけの独占業務です。
実務面では、遺言執行者として実際に財産を分配したり、不動産の名義変更や預金解約などの手続きを行ったりすることもあります。相続人がいない場合や未成年者が関与する場合には、家庭裁判所の選任を受けて相続財産管理人や特別代理人として職務を担うこともあります。
このように弁護士は、相続に関する法律問題から交渉・調停・訴訟まで一貫して対応できるため、特に相続人間で争いがある、もめそうであるといった「争族」の場面では欠かせない存在です。一方で、不動産登記や相続税の申告といった分野は司法書士や税理士の専門領域となるため、弁護士単独ではなく、他士業と連携して対応するケースが多く見られます。
司法書士の相続業務
司法書士は、主に登記や法務に関する手続きを専門とする士業であり、相続の場面では特に不動産の名義変更に強みを持っています。相続が発生した際に、被相続人名義の土地や建物を相続人名義に変更する「相続登記」は司法書士の独占業務であり、相続手続きの中で最も依頼が多い業務の一つです。
また、近年は「遺産承継業務」と呼ばれる、相続財産の包括的な承継サポートも行っています。具体的には、相続人調査や相続関係説明図の作成、預貯金の解約や名義変更、株式や投資信託の相続手続きなど、相続財産の分配に関わる実務をまとめて代行できます。金融機関への手続きに強いのも司法書士の特徴です。
さらに、家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士の業務範囲に含まれます。たとえば、相続放棄や限定承認の申述書、成年後見開始の申立書など、裁判所提出書類を代理で作成し、依頼者の負担を軽減します。ただし、裁判や調停における代理人としての活動はできません。司法書士は「簡裁訴訟代理権」を持つ場合もありますが、それは140万円以下の民事事件に限られ、相続事件は対象外となることが多いため、相続トラブルそのものの代理交渉や訴訟は弁護士に依頼する必要があります。
司法書士に依頼する大きなメリットは、相続手続きに必要な戸籍収集から、不動産登記や金融機関の手続きまでを一括して任せられる点です。とりわけ、不動産が相続財産に含まれているケースでは、司法書士が中心となって相続業務を進めるのが一般的です。一方で、遺産分割を巡って相続人同士が対立している場合や、遺留分請求などの争いが生じている場合には、司法書士は交渉や代理ができないため、弁護士との連携が不可欠になります。
行政書士の相続業務
行政書士は、相続に関する書類作成や手続きのサポートを専門とする士業です。相続が発生した際に必要となる戸籍謄本や住民票の収集を代行し、相続関係説明図を作成することで、誰が相続人であるかを明確に整理できます。また、相続人間で合意した内容を正式な書面にまとめる「遺産分割協議書」の作成や、公正証書遺言の文案作成、必要書類の収集なども行政書士の重要な業務です。
さらに、行政書士は金融機関や保険会社に提出する各種手続き書類の作成支援も行い、相続手続きをスムーズに進める役割を担います。生前の相続対策として、エンディングノートの作成支援や任意後見契約書の作成を行うことも可能です。これにより、相続開始後の混乱を未然に防ぎ、手続きの負担を軽減できます。
ただし、行政書士には不動産の登記手続きや相続税の申告を行う権限はなく、相続人同士の争いが生じた場合の代理交渉や調停、訴訟への代理もできません。そのため、争いのある相続や税務が関わる場合には、司法書士や弁護士、税理士と連携することが重要です。
行政書士は、相続手続き全般を「書類作成のプロ」としてサポートすることで、相続人が安心して手続きを進められるよう支援する存在です。特に、争いのない相続や遺言・協議書の作成において、その専門性が発揮されます。
税理士の相続業務
税理士は、相続に関わる税務の専門家として、主に 相続税や贈与税の申告・節税対策 を担当します。相続が発生した場合、被相続人の財産を評価し、税額を計算して申告書を作成するのが基本的な業務です。財産には、不動産や預貯金、株式、非上場会社の株式などさまざまなものが含まれますが、税理士はそれらの財産を正確に評価し、適正な税額を算出します。
また、税理士は生前の相続対策として、贈与の活用や養子縁組、生命保険の利用など、相続税の節税プランを提案することも可能です。相続後に配偶者や子どもが次に相続する「二次相続」を見据えた財産承継のアドバイスも行い、将来の相続税負担を軽減する支援をします。
さらに、相続税の申告後に税務署から調査が入った場合には、税務調査への立会いや対応も税理士の業務範囲です。これにより、申告内容の正確性を担保し、万一のトラブルにも対応できます。
ただし、税理士は不動産の登記や遺産分割協議書の作成、調停・訴訟の代理など、相続に関する法務手続きは行えません。そのため、争いがある場合は弁護士、登記が必要な場合は司法書士、書類作成が必要な場合は行政書士と連携して対応することが重要です。
税理士は、相続税の申告と節税対策を通じて、相続人が安心して財産を承継できるよう支援する専門家です。相続財産が基礎控除額を超える場合には、必ず相談しておきたい存在といえます
相続・困りごと別のまとめ
| 相談内容・困りごと | 推奨する専門家 | ポイント |
|---|---|---|
| 遺産分割でトラブルになりそう | 弁護士 | 交渉や調停、訴訟まで代理可能。争いがある場合は最優先。 |
| 遺言書を作りたい/遺言執行者に就任してほしい | 弁護士、行政書士 | 弁護士は法的チェック・執行も可能。行政書士は書類作成支援。 |
| 相続人調査・相続関係説明図作成 | 行政書士、司法書士 | 戸籍収集や家系図作成など書類整理のプロ。 |
| 不動産の名義変更(相続登記) | 司法書士 | 不動産登記の代理が可能。金融機関手続きも含め一括対応可能。 |
| 預貯金・株式・投資信託の相続手続き | 司法書士 | 遺産承継業務として一括サポート。金融機関手続きに強い。 |
| 相続税・贈与税の申告・節税対策 | 税理士 | 財産評価、節税プラン作成、税務調査対応まで可能。 |
| 相続放棄や限定承認の手続き | 弁護士、司法書士 | 家庭裁判所への申述書作成・提出の代理。 |
| 成年後見制度を利用したい/権利擁護 | 弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士 | 認知症などで財産管理が必要な場合に関与。 |
| 争いがなく、書類整理だけしたい | 行政書士 | 遺産分割協議書、遺言書の作成など。書類作成の専門家として便利。 |
| 将来の相続対策や資産承継の相談 | ファイナンシャルプランナー、民間相続コンサル | 生前贈与や家族信託など、ライフプランに沿ったアドバイス。 |
民間資格について
相続分野には、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの国家資格のほかに、相続診断士や相続アドバイザー、ファイナンシャルプランナー(FP)、終活カウンセラーなどの民間資格があります。これらの資格を持つ専門家に相談する場合には、いくつか注意点があります。
まず、民間資格者は、法律上の独占業務を行うことはできません。たとえば、遺産分割協議書の作成や不動産登記、相続税の申告、調停や訴訟での代理などは、国家資格者である弁護士、司法書士、行政書士、税理士の独占業務です。民間資格者は基本的に「相談・助言・情報提供」に留まるため、実務上の手続きを依頼する場合には、国家資格者に引き継ぐ必要があります。
次に、民間資格には信頼性に差があります。同じ相続診断士や相続アドバイザーという資格でも、認定団体の基準や取得の難易度は異なり、短時間の講座や通信教育で取得できるものもあります。そのため、資格の有無よりも、その人の実務経験や士業との連携体制を確認することが重要です。
さらに、民間資格者は多くの場合、相談者の状況を整理し、必要に応じて弁護士や税理士などの国家資格者につなぐ役割を担います。実際の登記や税務申告を代行することはできないため、「どの士業に依頼すればよいかをアドバイスしてくれるコンサル的な存在」と考えるのが適切です。
注意すべき点として、民間資格者の中には、金融機関や保険会社の商品販売を目的として資格を取得している場合もあります。この場合、中立的な立場ではなく、自社商品を勧める意図が含まれることがあります。そのため、相談する際には、報酬体系や商品の販売有無を必ず確認することが大切です。
相続に関する民間資格
調べ切れていないだけでもっとあるかもしれません。
相続特化系
- 相続診断士(一般社団法人 相続診断協会)
- 上級相続診断士
- 相続アドバイザー(NPO法人 相続アドバイザー協議会)
- 上級相続アドバイザー
- 相続士(一般社団法人 相続士協会)
- 上級相続士
- 相続手続カウンセラー(一般社団法人 相続手続カウンセラー協会)
- 相続コーディネーター
- 相続実務士
- 相続プランナー
- 相続カウンセラー
- 相続実務士(日本相続実務協会)
- 相続支援コンサルタント
終活・エンディング系
- 終活アドバイザー(一般社団法人 生活文化総合支援機構)
- 終活カウンセラー(終活カウンセラー協会)
- 上級終活カウンセラー
- 終活ライフケアプランナー
- エンディングノートプランナー
- 終活士(日本終活士協会)
- 終活ガイド(一般社団法人 終活協議会)
信託・事業承継系
- 家族信託コーディネーター
- 家族信託専門士(一般社団法人 家族信託普及協会)
- 信託実務検定
- 信託コーディネーター
- 事業承継アドバイザー
- 事業承継プランナー
- 事業承継士(一般社団法人事業承継協会)
FP・コンサル・その他
- ファイナンシャルプランナー民間認定(AFP/CFPはFP協会の認定資格)
- 相続FP(相続に特化したFP資格)
- ライフコンサルタント(保険会社系)
- トータルライフコンサルタント(生命保険協会)
- 遺品整理士(遺品整理士認定協会)
- 財産管理マスター
- 家族法務コンサルタント
- 遺言執行アドバイザー
民間資格者に相談する際は、実務経験や士業との連携体制を重視すべきです。相続は法律・税務・不動産・金融が複雑に絡むため、資格だけでは十分な対応ができません。実績や具体的に何をサポートしてくれるのかを事前に確認することが、安心して相談を進めるためのポイントです。
お気軽にお問い合わせください。0475-44-4106受付時間 7:30‐22:00 年中無休
お問い合わせはこちら メールは24時間受付