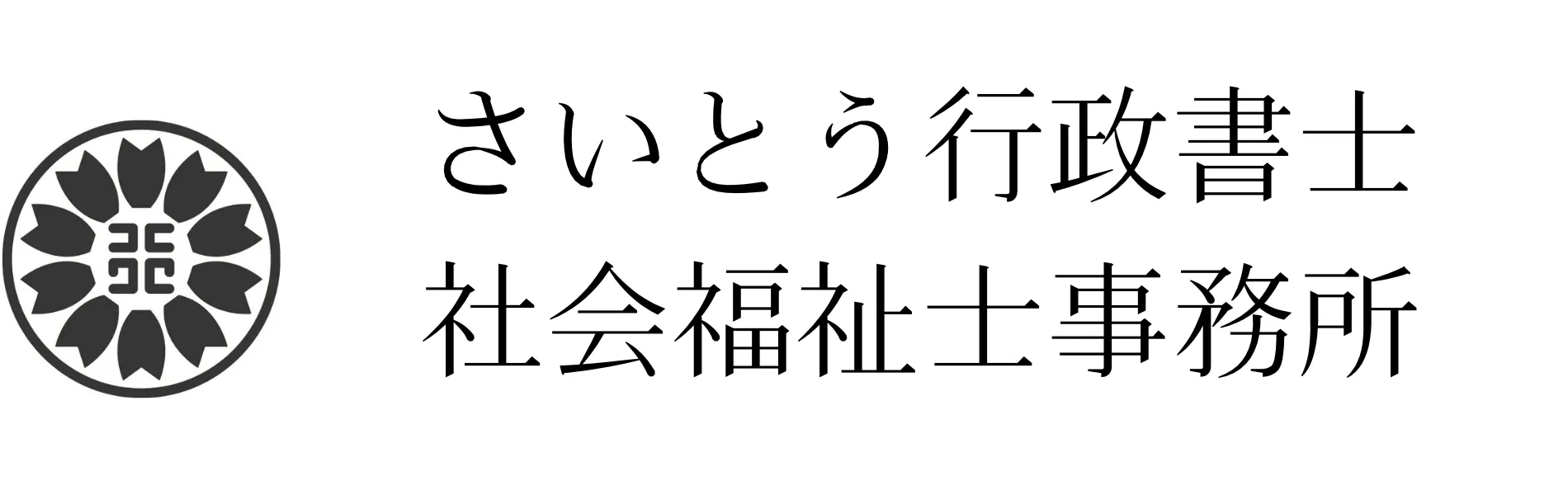尊厳死宣言公正証書について

「尊厳死公正証書」とは、本人が将来、回復の見込みがなく延命治療のみが続くような状態になった場合に、人工呼吸器や胃ろう、心臓マッサージなどの延命措置を望まないという意思を、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書の形で残すものです。
尊厳死と安楽死について
安楽死は積極的に医師が薬物の投与などで死に至らしめるのに対して、尊厳死は本人の意志で延命治療をしないという選択をし、自然な死を迎えることです。前者を積極的安楽死、後者を消極的安楽死と言ったりします。
| 項目 | 尊厳死 | 安楽死 |
|---|---|---|
| 定義 | 延命治療を行わない/中止することで自然な死を迎える | 医師などが薬物投与等で積極的に死をもたらす |
| 行為の性質 | 「治療をやめる/しない」行為 | 「死を引き起こす」行為 |
| 死の方向 | 自然死の受容 | 人為的に死期を早める |
| 本人の意思 | 尊重される(尊厳死宣言などで明示することが望ましい) | 本人の意思があっても日本では原則認められない |
| 法的扱い(日本) | 明確な法律はないが、条件次第で容認される余地あり | 嘱託殺人・自殺幇助などに該当し違法 |
| 主体 | 医師は延命治療を控える/中止する | 医師が致死的薬物を投与する |
| 代表例 | 人工呼吸器を外す、胃ろうをしない | 致死量の薬物を投与して苦痛から解放する |
尊厳死 安楽死の要件とは
| 尊厳死(延命治療の中止・不開始) | 安楽死(積極的安楽死) |
|---|---|
| 東海大学病院事件(1991 横浜地裁) 1. 回復不能 2. 耐えがたい苦痛 3. 本人の意思表示 4. 医師の相当な判断 | 東海大学安楽死事件(1995 横浜地裁) 1. 耐えがたい肉体的苦痛 2. 死が避けられず目前 3. 本人の明示的な意思表示 4. 医学的・倫理的に妥当な方法 |
| 明確な法律はないが、条件次第で容認される余地あり | 原則違法(嘱託殺人罪・自殺幇助罪などに該当) |
| 多くの国で条件付きで尊重されている | オランダ・ベルギー・カナダなど一部の国で合法 |
尊厳死、安楽死ともに法律で認められているわけではありません。但し、尊厳死に関しては「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」が定められており、一定条件下で認められています。安楽死に関しては裁判所が示した要件は、あくまで「違法性が阻却される可能性がある条件」を整理したにすぎず、実際には積極的安楽死は認められていません。したがって、日本では現状「積極的安楽死=違法」、「消極的安楽死(尊厳死に近い形)=条件付きで容認されることがある」という扱いです。
延命治療とは
尊厳死や終末期医療の議論で中心となるのは 人工呼吸器・心肺蘇生・胃ろう・透析 などです
| 医療行為 | 内容 |
|---|---|
| 人工呼吸器 | 自発呼吸ができない場合に機械で呼吸を補助する |
| 心肺蘇生法(CPR) | 心停止時に心臓マッサージや電気ショックで蘇生を試みる |
| 点滴 | 静脈から水分・栄養を補給する |
| 経鼻経管栄養 | 鼻から胃へチューブを通して栄養を入れる |
| 胃ろう | 腹部に直接チューブを設置し栄養を注入する |
| 人工透析 | 腎臓が機能しない場合に機械で血液を浄化する |
| 昇圧剤・強心剤 | 血圧や心機能を薬で維持する |
| 血液製剤の投与 | 血液を補充して生命維持を図る |
| 体外循環装置(ECMO) | 重症呼吸不全・心不全で血液に酸素を供給する |
心肺蘇生は入院時に最初に確認されることが多いです。
入院が長引き、咀嚼、嚥下機能が低下したり認知機能が低下したりし、食事が取れなくなってくると経管栄養、中心静脈栄養、点滴の中から栄養摂取方法を医師から確認されます。この時、本人の意思が明瞭でないと家族が選択することになります。この選択は残りの寿命を左右する重要な選択になり、家族は苦渋の決断をしなければなりません。尊厳死宣言公正証書がある場合、その文書の内容が尊重されるため家族の精神的負担が軽くなると考えられます。
尊厳死宣言公正証書の文例
尊厳死宣言公正証書
私、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生、住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)は、
回復の見込みがなく、かつ死期が迫っていると医学的に判断された場合の
医療行為について、以下のとおり私の意思を明確にしておく。
第一条(延命治療の拒否)
私は、次の医療行為について、延命のみを目的とする場合には「行わないこと」を希望する。
希望する項目に☑を付すものとする。
□ 人工呼吸器の装着
□ 心肺蘇生術(心臓マッサージ、電気ショック、気管挿管等)
□ 強制的な経管栄養(胃ろう、経鼻栄養など)
□ 人工透析
□ 輸血
□ 点滴による延命のみの栄養補給
□ その他( )
第二条(苦痛の緩和)
私は、痛みや苦しみを和らげるための緩和医療(鎮痛剤、麻酔薬等)は
最大限に受けることを希望する。
第三条(家族・医師への要請)
私は、この宣言が私自身の自由意思に基づくものであることを確認する。
主治医をはじめとする医療従事者および家族に対し、私の意思を最大限尊重していただきたい。
第四条(効力)
この宣言は、私が判断能力を有している間に作成するものであり、
書面により撤回するまで有効とする。
以上、私の真意に基づき、本宣言を作成する。
令和〇年〇月〇日
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇〇〇 (実印)
(公証人の署名・押印)
注意点
1. 法的効力は限定的
- 日本には「尊厳死法」が存在せず、尊厳死の法律的根拠は明確でない。
- 公正証書にしても、絶対に尊重される保証はない(医師や病院によって対応が異なる)。
- あくまで「本人の意思を明示する強力な資料」という位置づけです。
2. 意思表示の明確化が必要
- 「どのような治療を望まないのか」を具体的に書くことが大切です。
- あいまいな表現だと医療現場で判断が困難になる。
3. 作成時の本人の判断能力
- 作成時に 意思能力(判断力)があること が前提。
- 認知症の進行後などでは作れないため、早めの準備が重要。
4. 家族との共有が不可欠
- 医師は家族の同意を重視する傾向がある。
- 本人が尊厳死宣言を残していても、家族が強く反対すると医師は延命措置を続ける場合がある。
- 作成後は家族と話し合い、共有しておくことが必須。
5. 定期的な見直しが望ましい
- 医療技術や本人の考えは変わりうる。
- 10年前に作ったまま放置していると、医療現場で「現在の意志との乖離はないか?」と疑われる可能性がある。
- 定期的に更新や再確認をするのが望ましい。
6. 医師・病院による対応差
- 病院によっては「尊厳死宣言公正証書」があっても対応しない場合がある。
※日本尊厳死協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年は9割を超えているといったアンケートが出ています。 - 事前にかかりつけ医や病院に相談しておくと安心。
まとめ
尊厳死宣言公正証書は 本人の意思を最も強力に示す手段 ですが、
- 法的拘束力がない
- 家族や医師の理解が不可欠
- 内容を具体的に記載する必要がある
といった点に注意が必要です。
わからないことなどはお気軽にご相談ください
尊厳死公正証書の原案作成、公証役場との打ち合わせ、同行など行います。また、遺言書作成、任意後見なども対応可能可能です。相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。0475-44-4106受付時間 7:30‐22:00 年中無休
お問い合わせはこちら メールは24時間受付